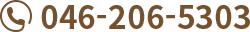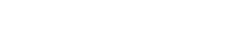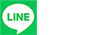こんにちは。座間市相武台、小田急線「相武台前駅」南口より徒歩1分にある歯医者「相武台ゆうデンタルクリニック」です。
子どもの歯並びや噛み合わせは、見た目の印象だけでなく、発音や咀嚼、全身の健康にも深く関わっています。
近年では、永久歯が生え揃う前の段階から矯正治療を始める早期矯正に注目が集まっており、そのなかでも床矯正(しょうきょうせい)は負担が少ない方法です。
特に、成長期の子どもの顎の発育を利用しながら、歯がきれいに並ぶスペースを作ることができるため、抜歯を避けたいと考える保護者の方に選ばれています。
今回は、床矯正とはどのような治療法か解説します。メリット・デメリットや治療期間、費用の目安についても解説しますので、お子さまの歯並びについてお悩みの方や、矯正治療を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
床矯正とは

床矯正(しょうきょうせい)とは、取り外し可能な装置を使い、成長期の子どもの顎の幅を広げることで、歯が正しく並ぶためのスペースを確保する矯正方法です。
歯に力を加えて動かすのではなく、顎の骨の発育をコントロールすることで、永久歯がきれいに並ぶ環境を整えることを目的としています。
この治療では、プレート型の装置を使用し、中央にあるスクリュー(ねじ)を保護者の方が定期的に回すことで、少しずつ顎の幅を広げていきます。一般的には小児期に行われることが多く、特に6〜12歳ごろの顎の成長が活発な時期に効果を発揮します。
また、装置は自分で取り外しができるため、食事や歯磨きがしやすく、日常生活への負担が少ないのも特徴です。永久歯が生えるスペースが足りないといった早期のサインに対応できる、予防的な意味合いもある矯正方法です。
床矯正のメリット

床矯正には、ほかの矯正方法にはない複数のメリットがあります。以下で詳しく見ていきましょう。
取り外しができるため衛生的
床矯正で使用する装置は、お子さん自身で簡単に取り外すことができるのが大きな特徴です。食事や歯磨きの際には装置を外せるため、口腔内を清潔に保ちやすく、虫歯や歯肉炎などのリスクを軽減できます。
特に固定式の装置を使用した治療では、装置まわりの清掃が不十分になりがちですが、床矯正なら普段通りに歯磨きができるため、保護者の方にとっても安心です。日々のケアがしやすい点は大きなメリットといえるでしょう。
痛みが少ない
床矯正は、装置のスクリューを少しずつ調整しながら顎の骨の幅を広げていく仕組みのため、強い力で急激に歯を動かすような治療と比べて、痛みや不快感が少ないのが特徴です。
成長期の子どもは骨がやわらかく、矯正による圧力にも順応しやすいため、無理のない力で顎の成長を促すことができます。
抜歯を避けられる可能性がある
矯正治療において、歯が並ぶスペースが十分にない場合には抜歯が必要になることがあります。
しかし、床矯正では顎の幅を広げることによってスペースを作るため、抜歯せずに済む可能性が高くなります。将来的に永久歯がすべて生え揃うことを見越して、計画的にスペースを確保することができるのは大きなメリットです。
成長を利用した自然な矯正が可能
床矯正は、成長期の子どもの顎の発育を活かして歯並びを整える治療法です。特に6歳から12歳ごろは、顎の骨がやわらかく成長も活発なため、この時期に治療を行うことで、自然なかたちで歯がきれいに並ぶためのスペースを作ることができます。
成長に逆らうのではなく、成長を味方にしながら進める矯正方法なので、身体への負担が少なく、仕上がりも自然な見た目になるのが大きな特徴です。
また、早期に顎の発育を整えることで、将来的に本格的な矯正が不要になったり、抜歯を避けられたりする可能性もあります。
床矯正のデメリット

一方で、床矯正には注意すべき点や制限もあります。メリットだけでなく、デメリットについても理解しておきましょう。
装置の装着時間が短いと効果が出にくい
床矯正の装置は、自分で取り外しができる反面、装着時間が不十分だと計画通りに効果が現れにくくなるという課題があります。一般的には、装置を1日12〜14時間以上装着する必要があります。
とくに小さなお子さんの場合、自分で装置の管理をするのが難しく、つい装着を忘れたり、嫌がって外したりすることも少なくありません。そのため、保護者の方のサポートが不可欠です。
決められた装着時間を守らなければ、治療期間が延びたり、十分な結果が得られなかったりする可能性があるため、家庭での協力体制が非常に重要になります。
発音しにくくなる
床矯正の装置を装着すると、舌の動きが制限され、特に装着初期には発音がしづらくなることがあります。サ行やタ行など、舌を使って発音する音が聞き取りにくくなるケースもあり、学校や日常生活での会話に支障を感じるお子さんもいます。
この発音のしにくさは、装置に慣れてくるにつれて徐々に軽減されることが多いですが、個人差があります。特に言語発達の途中にある子どもにとっては、一時的とはいえストレスに感じることもあるでしょう。
歯を動かすことはできない
床矯正は主に顎の幅を広げてスペースを作る治療法であり、個々の歯を直接移動させることはできません。そのため、歯並びの乱れが重度で、歯をピンポイントで動かす必要がある場合には、ほかの方法が選択されることがあります。
特にすでに永久歯が生え揃っている段階や、歯が大きく重なっているケースでは、床矯正だけで理想的な歯並びを得ることは難しい場合があります。
そのため、必要に応じて永久歯が生えそろってから、ワイヤー矯正などの他の治療と組み合わせて対応することがあります。
装着を嫌がる子どももいる
床矯正で使用する装置は取り外しができますが、それは同時に外したままにするリスクにもつながります。
特に慣れないうちは、装置を口に入れることを嫌がるお子さんも多く、保護者の方のサポートが重要になります。モチベーションを維持するために、装着の習慣づけや褒める工夫が必要です。
床矯正の適応年齢

床矯正は、顎の成長が活発な子どもを対象にした治療法です。
床矯正の効果が最も期待できるのは、乳歯から永久歯に生え変わる6〜12歳ごろです。この時期は、顎の骨がまだ柔らかく、成長も著しいため、装置による誘導がしやすいのが特徴です。
特に上顎の拡大は12歳を過ぎると難しくなることが多いため、早期の受診と判断が重要になります。永久歯がきれいに並ぶ土台を作ることができれば、将来的に本格的な矯正を回避できる可能性もあります。
床矯正の治療期間

治療期間は、顎の成長具合や歯並びの状態によって異なりますが、一般的には1〜3年程度が多いとされています。
ただし、装置の装着時間が不十分だったり、装置の調整が適切に行われなかったりすると、それ以上かかることもあります。
反対に、装着時間をきちんと守り、定期的な通院を欠かさなければ、スムーズに治療が進む傾向にあります。
床矯正の費用

床矯正の費用は、使用する装置の種類や治療期間、通院頻度によって異なりますが、一般的には20万〜40万円程度が相場です。
床矯正をはじめとした矯正治療は、基本的に保険適用の対象にはなりません。自由診療となるため、初診時に必ず費用の内訳を確認することが大切です。
まとめ

床矯正は、成長期の子どもの顎の発育を活かして、永久歯が並ぶスペースを確保する矯正方法です。装置の取り外しができるため衛生的で、痛みも少なく、抜歯を避けられる可能性があるなど、多くのメリットがあります。
一方で、装置の装着時間を守らないと効果が得られにくいといった注意点もあります。
適切な時期に始めることで、のちの本格的な矯正治療を回避できる場合もあるため、早めに相談することが重要です。お子さまの歯並びに不安がある場合は、まず歯科医院でカウンセリングを受けて相談しましょう。
小児矯正を検討されている方は、座間市相武台、小田急線「相武台前駅」南口より徒歩1分にある歯医者「相武台ゆうデンタルクリニック」にお気軽にご相談ください。
当院は、地域の皆様のお口の健康を守り、豊かな人生になるよう寄り添う事を理念にしています。一般歯科だけでなく、予防歯科や矯正治療、口臭治療、ホワイトニングなど、さまざまな診療にあたっています。



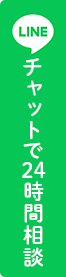

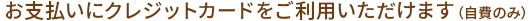
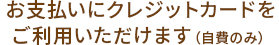





![Quacareer[クオキャリア]新卒歯科衛生士募集中|採用情報・見学申し込みはこちら](/common/img/bnr_hygienist01.jpg)
![Quacareer[クオキャリア]経験者歯科衛生士募集中|採用情報・見学申し込みはこちら](/common/img/bnr_hygienist02.jpg)