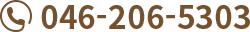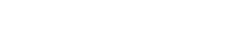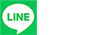こんにちは。座間市相武台、小田急線「相武台前駅」南口より徒歩1分の歯医者「相武台ゆうデンタルクリニック」です。
虫歯や歯周病、ケガなどで歯を失ったあと、「ブリッジにしましょう」と言われても、どのような治療なのか、入れ歯やインプラントと何が違うのか、よくわからないという方は少なくありません。
歯のブリッジ治療とは、失った歯の両隣の歯を土台にして、橋のように人工の歯を固定する方法です。取り外し式の入れ歯とは違い、しっかり固定されるため、噛み心地や見た目の自然さから選ばれることが多い治療法です。
この記事では、歯のブリッジとは何かという基本から、適用されるケース、種類、治療の流れ、メリット・デメリット、寿命や費用、インプラント・入れ歯との違いまで、順番にわかりやすく解説します。ブリッジ治療を検討されている方は、治療選択の参考にしてください。
歯のブリッジ治療とは

歯のブリッジ治療は、失った歯の両側に残っている歯を支えにして、連結した被せ物を装着する治療です。両隣の歯を削って土台となる形に整え、その上に土台の歯の被せ物と、失った部分を補う人工の歯が一体になった装置を接着して固定します。
このように橋を架けるような構造になるため、「ブリッジ」と呼ばれています。装着後は、噛む力を両隣の歯で分散しながら、失った歯の見た目と噛む機能を補うことができます。
一方で、支えとなる歯を削る必要があること、支えの歯に通常より大きな負担がかかることが特徴です。
そのため、治療前には土台となる歯の虫歯や歯周病の有無、歯を支えている骨や歯ぐきの状態、噛み合わせなどを十分に検査し、ブリッジに耐えられるかどうかを慎重に判断することが欠かせません。
どんなときにブリッジ治療が適用されるのか

ブリッジ治療が向いているのは、失った歯の本数が比較的少なく、両隣にしっかりした歯が残っている場合です。一般的には、連続した1本から3本程度の欠損に対して検討されることが多く、特に両隣の歯に十分な歯質と骨の支えがあり、強い噛む力に耐えられることが重要になります。
反対に、失った歯の本数が多い場合や、両隣の歯が大きな虫歯で弱っている、歯周病でぐらついている、根が短いなど、支えとしての余力が少ない場合には、ブリッジは適していないことがあります。
このようなケースでは、部分入れ歯やインプラントなど、別の治療法を検討した方が安全な場合もあります。
また、いちばん奥の歯を失った場合のように、欠損部の片側にしか歯が残っていないケースでは、通常の形のブリッジはできません。条件によっては片側だけで支える特殊なブリッジを検討することもありますが、適応は限られます。
ブリッジの主な種類

一口にブリッジといっても、支え方や削る量によっていくつかの種類があります。お口の状態や希望に応じて、適したタイプを選択していきます。
一般的な固定式ブリッジ
もっとも一般的なのが、失った歯の両隣の歯を削り、その2本を土台として真ん中の人工歯を支える固定式のブリッジです。3本分が一体となった形で作られることが多く、噛む力を両側に分散できるため、安定しやすい構造です。
多くの保険診療のブリッジや、自費診療のセラミックブリッジも、この形を基本としています。
接着ブリッジ(歯をほとんど削らないタイプ)
前歯を1本だけ失ったようなケースで、両隣の歯を大きく削りたくない場合に検討されるのが、接着ブリッジです。失った歯の両隣の歯の裏側に、薄い羽根のような金属やセラミックの板を接着し、その板に人工の歯を一体化させて固定します。
通常のブリッジと比べて、土台となる歯を削る量をかなり少なくできるのが利点ですが、接着面が限られるため、外れやすい、強い噛む力には向かないなどの制約があります。
適応できるかどうかは、噛み合わせや歯並び、歯の形などを詳しく診断して判断します。
カンチレバーブリッジ(片側支持のブリッジ)
両隣に歯がない、あるいは片側の歯だけがしっかりしている場合に検討されるのが、カンチレバーブリッジと呼ばれる片側支持のブリッジです。一本の歯、または複数の歯を土台として、その先に片持ち梁のように人工の歯を延長して作ります。
構造上、てこのような力がかかりやすく、土台の歯に大きな負担がかかるため、適応できる症例は限られます。
特に強い噛む力がかかる奥歯では慎重な設計が必要であり、場合によってはインプラントなど別の選択肢が優先されることもあります。
ブリッジ治療の流れと期間

ブリッジ治療は、いくつかのステップを踏んで進めていきます。お口の状態によって回数や期間は変わりますが、おおよその流れを知っておくと安心です。
初診・検査・治療計画
まず、現在のお口の状態を確認するために、レントゲン撮影や歯ぐきの検査、噛み合わせのチェックなどを行います。失った歯の本数や位置、両隣の歯の状態、歯周病の有無などを総合的に評価し、ブリッジが適しているかどうかを判断します。
この段階で、ブリッジ以外の選択肢として、入れ歯やインプラントの説明も行い、それぞれのメリット・デメリットや費用感を踏まえて、患者さんと一緒に治療方針を決めていきます。
土台となる歯の治療と形成
ブリッジを支える両隣の歯に虫歯や歯周病がある場合は、先にその治療を行います。神経の治療が必要な場合や、歯ぐきの炎症が強い場合は、この段階での治療期間がやや長くなることがあります。
土台となる歯の状態が整ったら、ブリッジを被せるために歯を削り、被せ物がぴったり合うように形を整えます。同じ日に、仮歯を装着して見た目や噛む機能を一時的に回復させることが一般的です。
型取り・ブリッジの製作
土台の形が整ったら、専用の材料で歯型を採り、歯科技工士がブリッジを製作します。素材や本数にもよりますが、完成までに通常1〜2週間ほどかかります。その間は仮歯で過ごしていただき、日常生活に大きな支障が出ないようにします。
ブリッジの装着・調整
>完成したブリッジをお口の中に試適し、噛み合わせや見た目、歯ぐきとのフィット感などを確認します。問題がなければ、専用の接着剤でしっかりと固定します。装着後しばらくは、噛み心地や話し方に少し違和感を覚えることがありますが、多くの場合、数日から数週間で慣れていきます。
通院回数と治療期間の目安
虫歯や歯周病の治療がほとんど必要ない場合、ブリッジ治療自体は2〜3回の通院で完了し、期間にするとおよそ数週間から1〜2か月程度で終わることが多いです。
ただし、支えとなる歯の状態が悪い場合や、歯ぐきの治療が必要な場合は、その分期間が延びることがあります。
ブリッジ治療のメリット

ブリッジ治療には、見た目や使い心地、治療期間などの面でさまざまな利点があります。治療法を選ぶ際には、これらのメリットを理解しておくことが大切です。
見た目が自然で審美性を高めやすい
自費診療のブリッジでは、セラミックやジルコニアといった白くて透明感のある素材を選ぶことができ、周囲の歯の色や形に合わせて細かく調整できます。そのため、天然の歯に近い自然な見た目を再現しやすく、特に前歯のように目立つ部分では、笑ったときの印象を大きく改善することが期待できます。
保険診療の場合でも、前歯では白い材料を用いたブリッジが選択できるため、金属色が目立つことを避けたいという方にも対応しやすい治療法です。
固定式で違和感が少なく、外れにくい
ブリッジは土台となる歯に接着剤でしっかり固定するため、取り外し式の部分入れ歯と比べて、装着時の違和感が少ないことが多いです食事中に動いたり外れたりする心配が少なく、自分の歯に近い感覚で噛める点を評価される方が多く見られます
また、取り外しの必要がないため、日常のケアも基本的には他の歯と同じように歯ブラシや補助清掃用具で行うことができます。毎食後に入れ歯を外して洗うことに抵抗がある方にとっても、受け入れやすい治療です。
外科手術が不要で、治療期間も比較的短い
インプラントのように顎の骨に人工歯根を埋め込む外科手術が不要なため、身体への負担が比較的少ない治療法といえます。全身疾患や服用中のお薬の影響で外科手術に不安がある方にとって、選択肢になりやすい点も特徴です。
治療期間も、支えとなる歯の状態が整っていれば、型取りから装着まで数週間から1〜2か月程度で完了することが多く、早めに噛む機能を回復したい方に向いています。
噛む機能や発音の回復が期待できる
失った歯をそのままにしておくと、噛みづらさだけでなく、発音がしにくくなることや、周囲の歯が倒れ込んで歯並びや噛み合わせが乱れることがあります。
ブリッジで欠損部を補うことで、噛む機能や発音を改善し、残っている歯の位置が大きくずれてしまうことを防ぎやすくなります。
特に奥歯を失った場合、ブリッジによって噛む面を回復させることで、硬いものや繊維質の多い食べ物も噛みやすくなり、食事の満足度の向上につながることが期待できます。
ブリッジ治療のデメリット・注意点
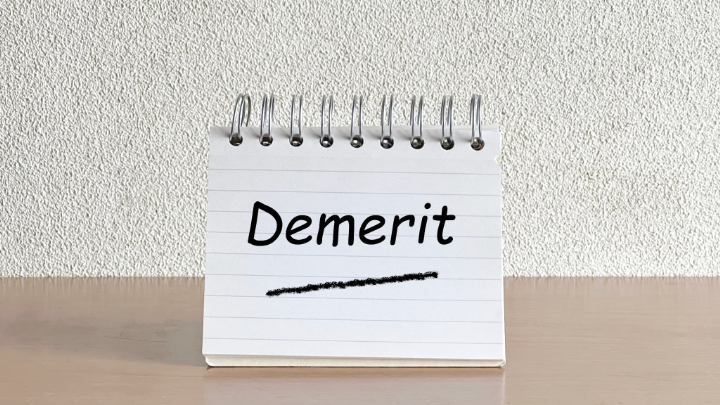
ブリッジ治療には多くの利点がある一方で、注意しておきたいデメリットやリスクも存在します。これらを理解したうえで、自分に合った治療かどうかを検討することが大切です。
健康な歯を削る必要がある
ブリッジを装着するためには、失った歯の両隣にある歯を土台として利用します。その際、たとえ虫歯のない健康な歯であっても、被せ物がしっかりと装着できるように周囲を削る必要があります。
歯は一度削ると元には戻らず、削る量が多いほど歯の神経に近づき、将来的にしみやすくなったり、神経の治療が必要になったりする可能性が高まります。長期的に見ると、削った歯の寿命が短くなるリスクがあることは、知っておく必要があります。
支えとなる歯に負担が集中しやすい
ブリッジは、失った歯の分の噛む力を両隣の歯が代わりに受け止める構造です。そのため、支えとなる歯には、本来その歯だけでは受けないはずの負担がかかり続けます。
長い期間この状態が続くと、支えの歯の根が割れてしまったり、歯の周りの骨が減ってぐらついてきたりするリスクが高まると考えられています。特に、2本以上の歯が連続して欠損している場合や、噛む力が強い方の場合には、設計に無理がないか慎重な検討が必要です。
虫歯や歯周病のリスクが高くなることがある
ブリッジは複数の歯が一体となった構造のため、歯と歯ぐきの境目や、人工の歯の下の部分など、汚れがたまりやすく磨きにくい場所が生じやすくなります。歯ブラシだけでは届きにくい部分も多く、プラークや食べかすが残りやすいことが特徴です。
その結果、支えとなる歯が虫歯になったり、歯ぐきに炎症が起きて歯周病が進行したりするリスクが高まる場合があります。
特に保険診療の金属製ブリッジでは、経年変化によって金属と歯の間にわずかな隙間が生じ、そこから虫歯が広がることもあります。
適用できない、または慎重な検討が必要なケース
ブリッジは万能な治療法ではなく、すべての症例に適用できるわけではありません。支えとなる歯が重度の虫歯や歯周病で弱っている場合や、根が短い場合、すでに大きな被せ物が入っていて余力が少ない場合などは、ブリッジをかけることでかえってその歯を早く失ってしまうおそれがあります。
また、連続して多くの歯を失っている場合や、噛み合わせの力が非常に強い場合、歯ぎしりや食いしばりが強い場合なども、設計によってはトラブルが起こりやすくなります。
このようなケースでは、インプラントや部分入れ歯など、別の方法を含めて総合的に検討することが重要です。
ブリッジの寿命と長持ちさせるポイント

ブリッジは一度入れたら一生ものというわけではなく、一定の寿命があります。ただし、日々のケアや設計の工夫によって、持ちを良くすることは十分に可能です。
ブリッジの平均的な寿命
ブリッジの平均的な使用年数は、おおよそ7〜8年程度とされています。実際には、支えとなる歯の状態や噛み合わせ、使用している素材、清掃状態などによって大きく変わり、10年以上問題なく使えているケースもあれば、数年でトラブルが生じるケースもあります。
研究報告では、条件の良い歯を土台にしたブリッジでは、10年後に多くが機能しているというデータもありますが、長期的には支えの歯の虫歯や歯周病、歯根の破折などが原因で再治療が必要になることが少なくありません。
特に、神経を残せた歯を土台にした場合の方が、長く安定しやすい傾向があるとされています。
ブリッジの寿命を縮める主な原因
ブリッジの寿命を左右する大きな要因として、支えとなる歯の虫歯や歯周病、噛み合わせの負担、清掃不良による汚れの蓄積などが挙げられます。ブリッジの一部が外れているのに気づかず使い続けてしまい、その隙間から虫歯が広がって歯根が割れてしまう、といったケースも見られます。
また、複数本をまとめて補うロングスパンのブリッジや、片側だけで支える延長型のブリッジは、どうしても支えの歯にかかる負担が大きくなり、トラブルが起こりやすい傾向があります。これらの設計を選ぶ場合には、特に慎重な診断とメンテナンスが重要です。
長持ちさせるための日常ケア
ブリッジをできるだけ長く使うためには、毎日のセルフケアが欠かせません。歯ブラシだけでは届きにくい部分が多いため、ブリッジ専用のフロスやスレッダー付きフロス、歯間ブラシなどを併用し、人工の歯の下や支えの歯の周囲の汚れを丁寧に取り除くことが大切です。
また、氷や硬いせんべいなど非常に硬いものを同じ場所で噛み続けると、ブリッジや支えの歯に過度な負担がかかり、破損の原因になることがあります。
食生活の中で、極端に硬いものを避ける、左右バランスよく噛むといった工夫も、ブリッジを守るうえで役立ちます。
定期的な歯科メンテナンスの重要性
セルフケアに加えて、歯科医院での定期的なチェックとクリーニングも、ブリッジを長持ちさせるうえで非常に重要です。専門的な器具を用いたクリーニングで、日常のブラッシングでは落としきれない汚れを除去し、支えの歯や歯ぐきの状態を細かく確認していきます。
定期検診では、ブリッジの接着状態や噛み合わせの変化も確認できるため、問題が小さいうちに調整や修理を行うことができます。ブリッジを装着したあとは、少なくとも数か月〜半年に一度のペースでの受診を心がけることが望ましいといえます。
ブリッジ治療の費用

ブリッジ治療の費用は、保険診療か自費診療か、何本分の歯を補うか、どの素材を選ぶか、支えとなる歯の事前治療がどの程度必要かによって変わります。ここでは、考え方の目安をお伝えします。
保険診療でのブリッジ
健康保険が適用されるブリッジでは、使用できる素材や部位に制限があります。奥歯では銀色の金属製ブリッジが基本となり、前歯では金属のフレームに白い樹脂を貼り付けた前装冠と呼ばれるタイプが用いられます。
保険診療の場合、自己負担は3割負担の方で、前歯のブリッジ1本あたりおよそ1〜2万円台、奥歯では1本あたり1万円前後になることが多いとされています。
ただし、実際の金額は本数や治療内容、医院によって異なりますので、詳細は受診時にご確認ください。
自費診療でのブリッジ
見た目や耐久性、金属アレルギーへの配慮などを重視したい場合には、自費診療のブリッジが選択肢となります。セラミックやジルコニアなどの素材を用いることで、天然歯に近い色合いや透明感を再現しやすく、金属を使わない設計も可能です。
自費診療の費用は、選ぶ素材や本数によって幅がありますが、1本あたり数万円から十数万円程度になることが一般的です。
ブリッジは最低でも3本分が一体となることが多いため、全体としては数十万円規模になる場合もあります。費用と見た目、耐久性のバランスを踏まえて、担当医とよく相談して決めていくことが大切です。
素材による違いと選び方のポイント
金属のブリッジは強度に優れ、奥歯の強い噛む力にも対応しやすい一方で、見た目が金属色で目立つことや、金属アレルギーの懸念があることが短所です。前歯の保険ブリッジに使われる白い樹脂は、時間とともに変色やすり減りが起こりやすい傾向があります。
セラミックやジルコニアは、自然な見た目と高い耐久性を兼ね備えており、金属アレルギーの心配が少ない点が利点です。
前歯では審美性を重視してオールセラミックやジルコニアを選び、奥歯では強度を重視してジルコニアを選ぶ、といった選択が考えられます。
メンテナンスにかかる費用も考慮する
ブリッジを長く使うためには、定期的な歯科検診とクリーニングが欠かせません。これらは多くの場合保険診療の範囲で受けられますが、年に数回の通院が必要になります。
また、経年とともに支えの歯に虫歯や歯周病が生じた場合には、その治療費や、場合によってはブリッジの再製作費用がかかることもあります。初回の費用だけでなく、長期的なメンテナンス費用も含めて検討することが、治療法選択の際には重要です。
インプラントや入れ歯との違い

歯を失ったときの主な治療法には、ブリッジのほかにインプラントと入れ歯があります。それぞれ構造や特徴が異なるため、ご自身の希望やお口の状態に合わせて選ぶことが大切です。
ブリッジとインプラントの違い
インプラントは、チタン製などの人工歯根を顎の骨に埋め込み、その上に人工の歯を被せる治療法です。周囲の歯を削らずに済み、失った歯だけを独立して補うことができる点が大きな特徴です。
ブリッジと比べた場合、インプラントは噛む力を直接骨で受け止めるため、両隣の歯への負担が少なく、長期的に見て残っている歯を守りやすいと考えられています。
一方で、外科手術が必要であること、治療期間が数か月に及ぶこと、自費診療となり費用負担が大きくなりやすいことがデメリットとして挙げられます。
ブリッジは外科手術が不要で、治療期間も比較的短く、保険診療の選択肢もあるため、費用を抑えやすい点が利点です。
その代わり、支えとなる歯を削る必要があり、その歯に負担がかかることが避けられません。どちらが適しているかは、全身状態やお口の状況、費用面などを含めて総合的に判断する必要があります。
ブリッジと入れ歯の違い
入れ歯は、取り外し式の装置で、部分的に歯を失った場合の部分入れ歯と、すべての歯を失った場合の総入れ歯があります。部分入れ歯では、残っている歯に金属のバネなどをかけて固定するのが一般的です。
ブリッジと比べると、入れ歯は隣の歯を大きく削らずに済み、複数本の歯を同時に補うことができる点が利点です。ただし、取り外し式であるため、装着時の違和感や、食事中に動きやすい、発音しづらいといった問題が生じることがあります。
また、バネをかける歯に負担がかかり、その歯の寿命が短くなる場合もあります。
ブリッジは固定式で違和感が少なく、噛む力も伝わりやすい一方で、支えとなる歯を削る必要があり、本数が多い欠損には対応しにくいことがあります。歯をできるだけ削りたくない方や、多くの歯を失っている方には、入れ歯やインプラントを含めた検討が必要になります。
まとめ

歯のブリッジ治療は、失った歯の両隣の歯を土台として、橋をかけるように人工の歯を装着する方法です。固定式で違和感が少なく、見た目も自然に仕上げやすいことから、歯を1本から数本失った場合によく選ばれる治療のひとつです。
一方で、健康な歯を削る必要があること、支えとなる歯に通常より大きな負担がかかること、清掃が難しい部分ができて虫歯や歯周病のリスクが高まることなど、注意すべき点もあります。
ブリッジの寿命は一般的に7〜8年程度とされていますが、支えの歯の状態や日々のケア、設計の工夫、定期的なメンテナンスによって、大きく変わってきます。
入れ歯やインプラントなど、他の治療法にもそれぞれ利点と欠点があります。どの方法が適しているかは、失った歯の本数や位置、残っている歯や歯ぐきの状態、全身の健康状態、費用面や治療期間に対するご希望などによって、一人ひとり異なります。
ブリッジ治療を検討されている方、インプラントや入れ歯との違いを詳しく知りたい方は、を検討されている方は、座間市相武台、小田急線「相武台前駅」南口より徒歩1分にある歯医者「相武台ゆうデンタルクリニック」にお気軽にご相談ください。
当院は、地域の皆様のお口の健康を守り、豊かな人生になるよう寄り添う事を理念にしています。一般歯科だけでなく、予防歯科や矯正治療、口臭治療、ホワイトニングなど、さまざまな診療にあたっています。



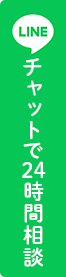

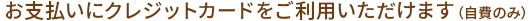
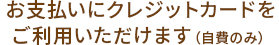





![Quacareer[クオキャリア]新卒歯科衛生士募集中|採用情報・見学申し込みはこちら](/common/img/bnr_hygienist01.jpg)
![Quacareer[クオキャリア]経験者歯科衛生士募集中|採用情報・見学申し込みはこちら](/common/img/bnr_hygienist02.jpg)