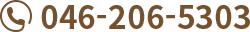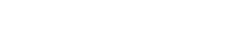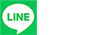歯がしみる

冷たい水を飲んだ時や、歯みがきの際に歯がキーンとしみる。多くの患者様が経験するこの感覚は、医学的に知覚過敏と呼ばれる症状の一つです。
しかし、むし歯でも同じような症状が現れることもあるため、混乱している方も少なくありません。ここでは知覚過敏とむし歯の違いについて解説します。
歯がしみる症状の正体とは?
はじめに、歯がしみるという症状の医学的なメカニズムを確認しておきましょう。
歯の構造としみる感覚のメカニズム
歯は外側から順に「エナメル質」「象牙質」「歯髄(神経)」で構成されています。エナメル質は人体で最も硬い組織で、熱や冷たさを遮断する役割を担います。
しかし、何らかの原因でエナメル質が薄くなったり、歯ぐきが下がって象牙質が露出したりすると、その内部にある象牙細管と呼ばれる微細な管が外部環境にさらされます。象牙細管の中には歯髄へとつながる液体が満たされており、冷水やブラッシングによる刺激で液体が移動します。
この液体の動きが神経を刺激し、「キーン」とした痛みに似たしみる感覚として脳に伝わるのです。これを流体力学説といい、知覚過敏の代表的な発症メカニズムとして広く知られています。
一時的な痛みと持続的な痛み
歯がしみる症状には大きく分けて二種類があります。冷たいものや甘いものに触れた瞬間にだけ短時間しみる「一過性の痛み」と、何もしていなくてもズキズキと持続的に痛む「持続性の痛み」です。
前者は知覚過敏に多く、刺激を取り除けばすぐに治まることが特徴です。一方、後者はむし歯や神経の炎症など、より深刻な疾患が疑われます。
歯がしみる=すべて知覚過敏ではない
患者様の多くが「歯がしみる=知覚過敏」と考えがちですが、実際にはむし歯が原因であることも珍しくありません。そのため、自己判断で放置すると症状が悪化することもあり、十分な注意が必要です。
知覚過敏と虫歯の違い
歯がしみるとき、特に区別が難しいのが「知覚過敏」と「むし歯」です。両者は似た症状を示しますが、発症の仕組みや経過には明確な違いがあります。
症状の出方の違い
知覚過敏は、冷たい飲食物や歯ブラシの接触といった特定の刺激で一時的にしみるのが特徴です。刺激がなくなればすぐに痛みは治まります。
これに対し、むし歯では初期こそ冷たいものだけが軽くしみる程度ですが、進行すると甘いものや熱いものでも痛みを感じるようになり、さらに進行すると何もしていなくてもズキズキと痛む持続痛に変わっていきます。
見た目の違い
知覚過敏では歯の表面に明らかな穴や変色がないことが多いのに対し、むし歯は黒や茶色に変色したり、穴が空いていたりと視覚的に異常が確認できることが多いです。ただし、初期むし歯では色の変化が目立たない場合もあり、歯科医師による検査が必要です。
進行の仕方の違い
知覚過敏は基本的に一過性で進行性の疾患ではありません。しかし、原因を放置すれば症状が繰り返し起こり、生活の質に影響を及ぼすことがあります。一方、むし歯は放置すると確実に進行し、最終的には歯の神経を侵すため抜歯が必要になるケースもあります。
治療の方向性の違い
知覚過敏は歯科用の薬剤塗布や生活習慣の改善でコントロールできる場合が多いですが、むし歯は自然治癒することはなく、必ず歯科的な治療が必要です。つまり、「痛みが一瞬で消えるか」「じわじわ悪化するか」が両者を見分ける重要なポイントとなります。
知覚過敏の主な原因
知覚過敏は単一の要因で起こるのではなく、歯や歯ぐきの構造的変化や生活習慣が複雑に関わって生じます。代表的な原因を、歯科医学的な視点から解説します。
歯ぎしり・食いしばり

就寝中のブラキシズム(歯ぎしり)や日中の食いしばりは、歯に過剰な力を与えます。この強い力は、咬耗(歯のすり減り)やくさび状欠損(歯頸部の欠け)を引き起こし、象牙質を露出させる原因となります。
特に噛み合わせが不均衡な患者様では特定の歯に負担が集中し、知覚過敏が進行しやすいことが知られています。慢性的な歯ぎしりは顎関節症のリスクとも関連するため、総合的な管理が必要です。
不適切なブラッシング圧

強いブラッシング圧や硬毛の歯ブラシの使用は、アブフラクション(歯頸部の摩耗)や歯ぐきの退縮を招きます。象牙質はエナメル質に比べて硬度が低く、摩耗しやすいため、象牙細管が露出しやすくなります。
さらに、過度なブラッシングは歯肉組織に微小な外傷を与え、炎症や歯肉退縮を助長することもあります。これにより、冷水や歯ブラシの毛先が直接象牙質に触れることで強いしみを感じるようになります。
歯周病や加齢による歯肉退縮

歯周病は歯槽骨や歯周靭帯を破壊し、歯ぐきが下がる原因となります。歯ぐきが退縮すると、通常は歯ぐきに覆われている歯根象牙質が露出し、知覚過敏が発生します。
加齢によっても歯肉退縮は自然に進行する傾向があり、歯周組織のボリュームが減少することで象牙質が刺激にさらされやすくなります。歯根象牙質はセメント質で覆われていますが、セメント質は薄く脆弱で摩耗に弱いため、保護力が低下すると知覚過敏を誘発します。
酸蝕症(さんしょくしょう)

酸蝕症とは、酸性飲料(炭酸飲料、スポーツドリンク、ワイン、柑橘類など)や胃食道逆流症(GERD)により、歯の表層エナメル質が化学的に溶解する現象です。エナメル質の臨界pH(約5.5)を下回る環境が繰り返されることで、ミネラルが溶出し歯が脆弱化します。
エナメル質が薄くなることで象牙質が露出し、知覚過敏のリスクが増加します。特に現代の食生活は酸性飲料の摂取機会が多く、酸蝕症に起因する知覚過敏が増加傾向にあると報告されています。
歯科医院で行う知覚過敏の治療法
知覚過敏は、象牙質に存在する象牙細管を通じて外部刺激が歯髄神経に伝わることで起こると考えられています(流体力学説)。そのため歯科医院での治療は、この象牙細管をいかに封鎖し、刺激を遮断するかが大きな目的となります。以下に代表的な方法を紹介します。
薬剤塗布による処置
最も基本的で第一選択とされるのが知覚過敏抑制剤の塗布です。
フッ化物
歯の再石灰化を促進し、エナメル質や象牙質の耐酸性を高めるとともに、象牙細管内に結晶を形成して物理的に封鎖します。
硝酸カリウム
歯髄神経の過剰な興奮を抑え、刺激伝達を抑制する働きがあります。即効性は低いものの、継続使用で効果が期待できます。
乳酸アルミニウム
象牙細管のタンパク質を沈殿させる作用があり、速やかに細管を閉鎖して刺激の侵入を防ぎます。短時間で効果を示す即効性が特徴で、知覚過敏の症状を早期に和らげたい患者様に有効とされます。
これらの薬剤を繰り返し塗布することで効果が安定し、比較的早期の知覚過敏なら数回の処置で改善が期待できます。
レジンやコーティング材による封鎖
薬剤のみで効果が不十分な場合は、歯科用レジンや特殊コーティング材で歯の表面を物理的に覆います。これにより象牙細管が直接外界に触れることを防ぎます。
レジン修復は歯の色調に合わせられるため審美性に優れますが、強い噛み合わせが加わる部位では摩耗や破損が生じやすいため、定期的な経過観察が不可欠です。
噛み合わせの調整
知覚過敏の背景には、しばしば咬合性外傷が関与しています。特定の歯に強い力が集中すると微細な亀裂やくさび状欠損が生じ、象牙質が露出します。歯科医院では咬合紙などを用いて噛み合わせの状態を確認し、必要に応じて咬合調整を行います。
さらに、就寝時の歯ぎしりや日中の食いしばりが疑われる場合は、マウスピース(ナイトガード)を作製し、歯にかかる力を分散させることが有効です。
歯周病の治療
知覚過敏は歯ぐきの退縮とも深く関係しています。歯周病が進行すると歯槽骨や歯周靭帯が破壊され、歯ぐきが下がって歯根象牙質が露出します。この場合は歯周病治療が欠かせません。
スケーリングやルートプレーニングにより歯石や細菌を除去し、歯ぐきの炎症を改善することで、象牙質の新たな露出を防ぎ、知覚過敏の再発リスクを減らすことができます。
自宅でできるケア・再発予防の工夫
知覚過敏は治療を受けて改善しても、日常生活の習慣によって再発することがあります。歯科医院での治療と並行して、自宅での正しいケアや予防習慣が重要です。
正しい歯みがき方法
強いブラッシング圧は歯の摩耗や歯ぐきの退縮を招き、知覚過敏を悪化させます。歯ブラシはやわらかめの毛を選び、小刻みにやさしく動かすことが大切です。
力を入れすぎないよう、歯ブラシの持ち方を鉛筆持ちに変えるだけでも改善につながります。電動歯ブラシを使用する場合も、圧をかけすぎないよう注意が必要です。
フッ化物配合の歯みがき剤
市販の歯みがき剤にはフッ化物や硝酸カリウムを配合した「知覚過敏用」の製品があります。フッ化物は歯質を強化し、硝酸カリウムは神経の興奮を抑える働きがあるため、日常的な使用で症状の緩和と再発予防が期待できます。
食生活の見直し
酸性の飲食物(炭酸飲料、スポーツドリンク、ワイン、柑橘類など)の過剰摂取は酸蝕症を引き起こし、知覚過敏の大きな要因となります。これらを摂る際は時間を区切り、ダラダラ飲み食いを避けることが重要です。
また、摂取後はすぐにゴシゴシ磨かず、水で口をすすいでから30分程度時間をおいてブラッシングすると、酸で軟化したエナメル質を守ることができます。
歯ぎしり・食いしばり対策
就寝中の歯ぎしりや日中の食いしばりは、歯の摩耗や欠損の原因となります。昼間に意識的にリラックスし「上下の歯を離す」習慣を持つことが予防につながります。重度の場合には歯科医院でナイトガードを作製し、自宅で装着することで歯を守ることができます。
定期的な歯科検診
自宅でのセルフケアだけでは歯ぐきや噛み合わせの問題を完全にコントロールすることは困難です。定期的な歯科検診を受けることで、知覚過敏の再発を早期に防ぐことができます。
特に歯周病やむし歯のリスクがある患者様は、症状が出る前から定期的な管理を受けることが推奨されます。
知覚過敏が気になる方へ

歯がしみる症状は、多くの患者様が経験する身近なトラブルですが、その正体は必ずしも「知覚過敏」だけではありません。冷たいものに一時的に反応する程度であれば知覚過敏の可能性が高いものの、痛みが持続する場合や見た目に変化がある場合はむし歯の進行も疑われます。
知覚過敏は歯ぎしりや不適切な歯みがき、歯ぐきの退縮、酸蝕症など生活習慣や全身的な要因と深く関わっており、放置すると症状が慢性化する恐れがあります。まずは自己判断せず歯科医院で診断を受け、原因を正しく把握することが大切です。
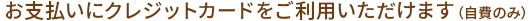
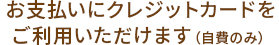








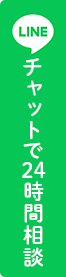
![Quacareer[クオキャリア]新卒歯科衛生士募集中|採用情報・見学申し込みはこちら](/common/img/bnr_hygienist01.jpg)
![Quacareer[クオキャリア]経験者歯科衛生士募集中|採用情報・見学申し込みはこちら](/common/img/bnr_hygienist02.jpg)