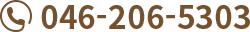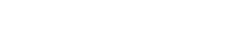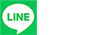歯のヒビ割れ

私たちの歯は人体で最も硬いエナメル質で覆われていますが、大きな力がかかることで割れたり、ヒビが入ったりします。歯のヒビを放置すると、さまざまなリスクが生じるため、症状に応じた治療が必要です。
ここでは歯にヒビが入ると何が起こるのか、放置するリスクや歯科医院で治療する方法などを座間市の相武台ゆうデンタルクリニックが解説します。
歯のヒビから起こる症状
歯にヒビが生じると、次に挙げる症状が現れます。
歯がしみる・痛い

歯にヒビが入ると、まず考えられる症状が痛みです。特に冷たい飲み物や甘いものを口にしたときにしみる感覚が出ることがあります。これはヒビによって象牙質が露出し、刺激が神経に伝わるためです。
また、噛み合わせのときに力がかかると痛むケースもあり、これはヒビが歯の内部に達している場合に起こります。
歯茎の腫れや炎症

ヒビが深く、歯の内部に細菌が侵入すると、歯の根の先に感染が起きることがあります。
この場合、歯茎が腫れたり、押すと痛みが出たりすることがあります。膿がたまると、歯茎に膿の出口(瘻孔)ができることもあります。
歯が黒ずむ

歯にヒビが入った部分には、段差が生じることで汚れがたまりやすくなります。
清掃性も低下するため、歯のヒビに沿った黒ずみが生じることが多いです。
自覚症状がないケースもある

実は、歯のヒビがあっても無症状のことは珍しくありません。特に表面の小さなヒビ(マイクロクラック)の場合、患者様が痛みや違和感を感じないことが多いです。
しかし、無症状だからといって放置してしまうと、将来的に症状が出たり、歯が割れて抜歯が必要になったりすることがあります。
歯にヒビができる原因
歯にヒビが入る主な原因としては、以下の3つが挙げられます。
- 強い噛み合わせの力
-

日常的に噛み合わせの力が強すぎる場合、特に奥歯には大きな負担がかかります。この持続的な力はエナメル質に微小な応力を生じさせ、時間の経過とともに亀裂(クラック)が発生することがあります。
歯ぎしり(ブラキシズム)や食いしばりは、無意識下で強い力がかかるため、医学的にはヒビの主因の一つとされています。こうした状態では歯の表層硬組織が疲労破壊を起こしやすく、注意が必要です。
- 外傷や硬いものの噛み込み
-

転倒して顔をぶつける、スポーツでボールが当たるなどの外傷は、急激な衝撃が歯に加わるため、エナメル質や象牙質に亀裂を生じさせるリスクがあります。
また、氷やナッツ、骨付き肉、あるいは硬い菓子類を噛んだ際に局所的に過大な力が集中し、歯にクラックが入ることがあります。
とくに修復物(詰め物や被せ物)がある歯は健全歯よりも脆弱で、割れやすいことが知られています。
- 歯の構造的弱さ
(マイクロクラック) -

歯の表面には、肉眼では見えない細かな亀裂(マイクロクラック)が存在することがあります。これらは、日常の咬合応力や経年変化、さらには歯質の脱灰・再石灰化過程によるミネラル構造の変化で生じるとされ、初期段階では症状を伴わないことが一般的です。
しかし、むし歯治療後に修復物と歯質の間に応力集中が起こると、マイクロクラックが拡大し、歯髄腔にまで達する深刻なクラックへ進行するリスクがあります。こうしたリスク因子は科学的根拠に基づき早期診断と対応が重要です。
歯のヒビを放置するリスク
歯のヒビを対処せずに放置していると、次に挙げる4つのリスクが生じるため十分な注意が必要です。
むし歯や感染症のリスク増加
ヒビが入った歯の内部には細菌が侵入しやすくなります。歯科医学的には、歯の亀裂を通じて細菌が象牙細管を伝わり、歯髄(神経や血管が存在する部分)に到達することで歯髄炎を引き起こすことがあります。
そのまま歯のヒビを放置した場合、感染は根尖(歯の根の先端)まで波及し、根尖性歯周炎や歯槽骨の骨吸収といった深刻な感染症に進展する可能性があります。これらの感染症は歯の保存を困難にし、最終的には抜歯が必要になる場合もあります。
歯の破折を招く
小さなヒビの段階では、接着性レジン修復などの保存的治療で対応可能な場合がありますが、亀裂が歯髄腔や歯根にまで進行すると、歯は構造的な問題を抱えるため、歯冠や歯根の破折を引き起こすことがあります。
特に歯根破折は予後不良とされ、保存治療の適応外になることが多く、抜歯が避けられないケースが多いです。臨床的には早期発見が歯の保存率を大きく左右します。
噛み合わせの悪化や周囲の歯への負担増
ヒビが入った歯は力学的強度が低下しており、咬合力の分布が不均衡になることで隣接歯や対合歯に過剰な負荷がかかります。
これにより、周囲の歯にマイクロクラックが生じたり、顎関節に負担がかかることで顎関節症や咀嚼筋の筋膜性歯痛を引き起こしたりすることがあります。
また、噛み合わせの悪化は二次的な歯列不正や歯周組織への悪影響を及ぼす場合があります。
治療の複雑化や費用の増大
ヒビが浅いうちに治療を行えば、エナメル質や象牙質の部分的な修復で済むことが多いですが、進行した場合は根管治療、歯冠補綴、場合によっては抜歯後のインプラント治療が必要になることがあります。
進行した症例は治療ステップが増え、使用する材料や技術の高度化によって治療費用や通院回数が大幅に増加します。したがって、患者様の負担を軽減するためにも、歯科医師と協力し、早期対応を心がけることが重要です。
歯にヒビがあると診断された場合は、症状がなくても放置せず、歯科医師と相談しながら適切な治療方針を立てることが大切です。
当院では拡大鏡やマイクロスコープを用いて精密な診断と治療を行い、患者様一人ひとりに最適な対応を提供しておりますので、気になる症状がある場合はお気軽にご相談ください。
歯のヒビは再石灰化で治る?
歯の表面にできたごく浅いヒビ(マイクロクラック)は、エナメル質の内部まで到達していないため、再石灰化によってある程度補修される可能性があります。再石灰化とは、唾液中に含まれるカルシウムやリン酸、フッ素などの成分がエナメル質の微細な損傷部に再び沈着し、補強される作用です。
しかし、これはあくまで初期の状態に限られ、目に見えるほどのヒビ割れや、象牙質まで到達しているヒビ、歯髄(神経)に近い深いヒビは、再石灰化では修復できません。
また、日常的に酸性の飲食物を摂取している場合や、歯ぎしり・食いしばりなどの強い力が歯にかかっている場合は、再石灰化よりむしろヒビの進行や拡大が懸念されます。
患者様ご自身でのケアとしては、フッ素配合の歯みがき剤を使用したり、正しいブラッシングを心がけたりすることでエナメル質の補強は期待できますが、進行したヒビには歯科医院での専門的な治療が必要です。
歯のヒビの主な治療法
歯にヒビが入った場合の歯科治療としては、主に以下の4つが挙げられます。
コンポジットレジン修復
浅いヒビや表面の亀裂の場合、コンポジットレジン(歯科用樹脂)で修復します。これは、むし歯治療などにも使われる白い樹脂素材で、歯の色に近く、自然な見た目に仕上がります。
治療はヒビの周囲をわずかに削り、レジンを流し込んで光で硬化させることで完了します。比較的短時間で済む治療ですが、ヒビが深部にまで及んでいる場合は適応外となることがあります。
インレーやクラウンによる補綴治療
中等度のヒビで、歯の一部が欠けるリスクがある場合は、インレーやクラウンで欠けた歯質を補う方法をとります。インレーは歯質の欠損部を補う詰め物で、歯の審美性や機能性、耐久性を回復できます。
クラウンは歯をぐるりと覆う被せ物で、噛み合わせ時の力を均等に分散させる効果があり、ヒビの進行を防ぐことにも大きく寄与します。
歯内療法(根管治療)
ヒビが歯の神経にまで到達している場合、歯髄が感染して炎症を起こし、強い痛みや腫れが生じることがあります。この場合、歯内療法(根管治療)が必要です。
歯の内部の神経や血管を取り除き、内部を清掃・消毒してから、根管内を薬剤で密封し、最後にクラウンなどで補強します。根管治療を行わないと、ヒビから細菌が侵入し、歯根の先端に病巣を作るリスクがあります。
抜歯・欠損補綴
歯根まで大きく破折したケースでは、保存治療が困難となるため抜歯が必要となります。抜歯後は、インプラント・ブリッジ・入れ歯といった欠損補綴を行います。
抜歯とその手順について
抜歯はまず局所麻酔を行い、痛みを感じない状態にします。その後、歯を支える歯根膜と歯槽骨(顎の骨)の間に器具を挿入し、歯を慎重に揺らしながら抜去します。
場合によっては歯の分割や歯槽骨の一部を削る必要があり、特に根が複雑な形をしている奥歯では技術を要します。
抜歯後は、止血を確認し、必要に応じて縫合を行い、感染予防のため抗菌薬が処方されることもあります。抜歯窩(抜歯後の穴)が治癒する過程では、血餅(かさぶたのような血の塊)が重要な役割を果たしますので、患者様には強いうがいや喫煙の回避など、適切な術後管理が指導されます。
インプラント治療

インプラントは、失った歯を補う方法の中でも近年主流となりつつある治療法です。抜歯後、顎の骨がしっかりと治癒し、骨量が十分であることを確認したうえで、チタン製の人工歯根(インプラント体)を顎骨に埋入します。
埋入後、骨とインプラントがしっかり結合する「オッセオインテグレーション」という現象が起こるまで、通常数ヶ月待機します。
その後、アバットメントという支台部を連結し、最終的にセラミック製の人工歯を装着します。インプラントの特長は、周囲の健康な歯を削る必要がないこと、しっかりと噛む力を回復できること、見た目が自然であることです。
ただし、インプラントは外科手術を伴うため、全身疾患の有無や歯茎・骨の状態を慎重に評価する必要があります。
ブリッジ治療

ブリッジは、欠損した歯の両隣の歯を削り、そこに橋渡しのように人工歯を連結させる治療法です。支台となる歯は削って被せ物(クラウン)に加工され、中央のダミーの人工歯(ポンティック)が空隙を埋める形になります。
ブリッジは固定式で違和感が少なく、比較的短期間で治療が完了しますが、健康な隣在歯を大きく削る必要があるため、歯の寿命を縮める可能性があります。
また、欠損部の歯茎とポンティックの間は清掃が難しく、むし歯や歯周病のリスクが高まることから、患者様には丁寧なホームケアと定期的な歯科受診が重要です。
入れ歯治療

入れ歯(義歯)は、失った歯を人工の装置で補う取り外し式の治療法です。部分入れ歯は残存歯に金属のクラスプ(留め具)をかけ、総入れ歯は歯茎に密着させて使用します。型取りや咬合(噛み合わせ)の調整を何度か行い、患者様に合わせた適合の良い入れ歯を作製します。
入れ歯のメリットは、周囲の歯をほとんど削らずに済み、外科手術も不要なことです。ただし、噛む力は天然歯やインプラントに比べると弱く、装着感に慣れるまで時間がかかる場合があります。また、適合が悪くなると痛みや咀嚼障害を引き起こすため、定期的な調整が欠かせません。
歯のヒビは早めの受診を

歯のヒビは放置するとむし歯や歯周病を引き起こしたり、ヒビの拡大によって歯の保存が難しくなったりすることがあります。噛み合わせの力のコントロールや、マウスピースを用いたナイトガードによる歯ぎしり防止など、予防的な対策も重要です。
気になる症状がある場合は、早めに歯科医院を受診し、的確な診断と治療を受けることをおすすめします。
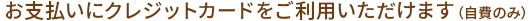
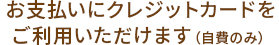








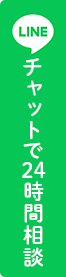
![Quacareer[クオキャリア]新卒歯科衛生士募集中|採用情報・見学申し込みはこちら](/common/img/bnr_hygienist01.jpg)
![Quacareer[クオキャリア]経験者歯科衛生士募集中|採用情報・見学申し込みはこちら](/common/img/bnr_hygienist02.jpg)